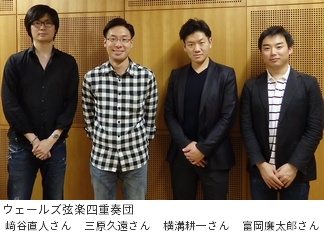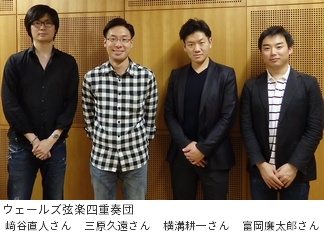
SQWシリーズに、今年から3年にわたるプログラムで出演していただけることになり、うれしく思います。プログラムは、シューベルトの後期にウィーンの作曲家を色々と組み合わせて、3回のシリーズを作っていただきました。
三原:シューベルトは、僕たちが長く弾いてきた作曲家で、とても思い入れがあります。3回のシリーズということでしたので、まずは、シューベルト後期の3つの弦楽四重奏曲を聴いていただこうと思いました。そして、3年連続で聴いてくださるお客さまのことを考えた時、あわせて新旧両方のウィーン楽派の音楽をぜひ聴いていただきたいと思ったのです。それで、今回演奏するベートーヴェンと、それにハイドン、モーツァルト、そして、ウェーベルンとベルクという新旧ウィーン楽派の作曲家でプログラムを組み立てました。いずれも弦楽四重奏の歴史の中で重要な作曲家です。
3回シリーズ初回となる今回、シューベルトは、第13番「ロザムンデ」を演奏します。組み合わせたベートーヴェンの第12番は、ウェールズQが10年前の結成時、最初に演奏した曲なのです。
ベートーヴェンの第12番とシューベルトの第13番「ロザムンデ」を組みあわせることはプログラムとして非常に意味があると思います。どちらも作品の完成が1824年。初演されたのは「ロザムンデ」の方が先で、1824年3月、ベートーヴェンの第12番は翌年の3月ですが、初演は両方ともシュパンツィヒQでした。同じウィーンという街にいたベートーヴェンとシューベルトが、同じ年に完成させた曲を、同じクァルテットが初演しているのです。当時のウィーンの人たちが聴いた順番に、ぜひお客さまにも聴いていただきたいと思いました。
富岡:ベートーヴェンの第12番は10年ぶりの演奏で、もちろん懐かしさもありますが、音楽的にも技術的にも当時とまるで違うことが、クァルテットを継続して良かったと思えることの1つです。
2008年にミュンヘン国際音楽コンクールに参加することに。
﨑谷:結成2年目に、クァルテットの奨学金をいただけることになり、原田幸一郎先生にその奨学金を、コンクールを受けたり、東京クヮルテットのマスタークラスに行くために使ったらどうかとアドヴァイスされました。それが、ミュンヘンのコンクールの応募締切の数か月前。
富岡:コンクールのために半年間でレパートリーを8曲増やさなければならないと聞いて、とりあえず図書館に行って楽譜を見て、曲を選ぶところから初めて・・・。
富岡:本当にきちんと集中してみんなが譜読みできた状態で、しっかり合わせができたのは、実質3か月でした。
本来クァルテットのコンクールは、3か月で集中的に勉強して受けるようなものではありません。何年か組んで、レパートリーを増やしていって、コンクールの時に追加するレパートリーは1曲か2曲あるかないかという状況が普通。ですから、ある種、ラッキーで獲れた賞かもしれませんが、このクァルテットを続けたいと思うきっかけになりました。その3か月間がすごく楽しかったのです。音楽家として幸せだなと思って。
﨑谷:コンクールの一次で、たまたま聴いたのがアマリリス弦楽四重奏団で、めちゃくちゃうまくて。同世代の本格的なクァルテットを、そこで初めて聴いたんですよ。もう僕たちは無理だなと。部屋に戻って、横溝は、帰りの飛行機のチケットを変更するための英語を勉強し始めたくらい(爆笑)。
それではミュンヘン国際音楽コンクール第3位という結果には、本当に驚かれたわけですね。
富岡:普通はコンクール入賞をステップアップとして、名刺がわりにクァルテットを続けていこうと思うのかもしれませんが、自分たちはその後続けるかなんて考えてないし、コンクールを受ける、ということしか考えていませんでした。次の本番がコンクールというだけです。続けていこうというのは、後から徐々にでした。クァルテットは長く弾いてみないと分からないし、メンバーがすごく大事だと思います。どんなにすぐれた奏者の人でも、出逢いがなければクァルテットはできないし、誰とでもできる訳でもない。人間としても、音楽家としても相性が良くないとできないだろうし。だから年を追うごとに、何があっても続けていこうと思うようになるのが自然ですね。
﨑谷:当時はまだ若かったし、各自やりたいこともあったし、こればかりはタイミングですね。柔軟にやってこられて、それぞれが音楽家として立派になっていて、それはクァルテットとしても、各自としても良かったのでは思います。
三原さんは、コンクール後に留学する段階で入って来られたのですね。
三原:クァルテットで留学してくれるメンバーを探すことは、簡単ではなかったと思います。
﨑谷:日本人にその感覚はないものね。
富岡:三原は大学を辞めてくれたんですよ。
三原:僕はすごくクァルテットをやりたかったのです。演奏するのも、聴くのも好きなので。僕にとってウェールズは、先輩のスター4人がやっていたクァルテットで、最初のベートーヴェン第12番から聴いていました。そこに僕が入るなんて、こんな、願ったりかなったりのことはない。もともと個人的に留学したいとも思っていたので、「はい、(大学は)すぐに辞めます」と。
富岡:僕らが提案したライナー・シュミット先生のところに行きたいというのもあったようです。
三原:当時から、僕が最も尊敬するクァルテット弾きでした。
横溝さんはその時、クァルテットを抜けるという難しい決断をしたのですね。
横溝:中学3年で徳永二男先生に習い始めた時から「大学を卒業した時にN響に入れるように育ててやる」と言ってくださっていたので、そこを目指すべきなのだろうなと。もちろんこのメンバーとクァルテットをやりたいと思って迷いましたし、原田先生が辞めない方がいいと引き留めてくださったのもありがたかったのですが、最終的には小さな頃からの夢をかなえる方向で決断しました。
バーゼルで師事したライナー・シュミット氏(ハーゲン弦楽四重奏団第2ヴァイオリン奏者)はどんな先生でしたか?
﨑谷:もう浮世離れしていますね。ずっと楽譜を読んでいる。
三原:音楽のことはもちろん、文学、絵画、映画など様々な芸術に精通していると思います。
富岡:四六時中、音楽のことを考えている方です。スコアを見ていて、なにか新しいことを発見すると突然「あああああ」と大きな声を出して。
﨑谷:興奮してね。レッスン中にですよ。点があるとか、そんなことですよ。
富岡:ここに点があるということは、つまり・・・となるわけです。ずっと、そんなことばかり考えているから、背中にハンガーをひっかけたまま、家から学校に来ても言われるまで気づかない。こういう人を音楽家っていうんだなと思いました。
帰国して横溝さんがヴィオラに戻られました。
﨑谷:留学中にスタイルが結構変わっていたので、自分たちが、3年間こういうことをやってきたということと、音楽的な話をして。
横溝:違う団体になっていました。
﨑谷:器用だから、どういう風にでもなじんでしまうのですね。最初は、見よう見まねで一緒に入ってもらって、あれこれやって2年ぐらいすると、もうカメレオンみたいに同色化していました。ある程度、そういう能力がないとできないスタイルですし、誰かが突出してリードするようなアンサンブルではないので、相性が良かったですね。
ウェールズQの演奏は、奥へ深く分け入っていく感じですね。
三原:外交的か内向的かと訊かれたら、内向的かもしれません。一般受けはしないんですけど。
﨑谷:アマリリスQを最初に聴いた時、彼らは、自分たちが今当たり前にやっていることをやっていたのだと思うのですが、当時はそのやり方が分からなかったんです。個々で見た時に、決して、ものすごくうまいプレーヤーがいるのかといえば、そうではないのですが、4人で弾いているとめちゃくちゃうまくなるというか。それがライナー・シュミット先生のところに行って分かったのです。

そのウェールズQのアプローチについて、一般の方にも分かるような例えはありますか。
﨑谷:サッカーチームみたいなものです。うまい選手を並べればいいってもんじゃない。音が鳴った瞬間、ボールを蹴った瞬間に、ここにこう来るだろうなと、同時にお互いの考えが並行していないと成り立たないのです。クリスティアーノ・ロナウドみたいな選手がいる訳ではないんだけど、4人で弾いていると、1人で弾いているよりも相乗効果が現れる、そういうアンサンブルの仕方ですね。楽譜をみた時にそういう発想になるので、そこがもう違うとは思います。オーケストラなどでは、今はここの音を捨てて、こちらにあわせてという作業をしていて、例えば、今は木管楽器がずれたから、バスの声部に合わせようとか、音ではなく指揮者に合わせようということをしている。でも、ずっとやっているクァルテットでは、4人が横にずっと一緒に動いているので、この中で誰かが、本番違う動きをしたとしても、ちゃんとこうやっていける。
富岡:誰かがくずれた時に、共倒れするようなアンサンブルともいえます。ある種、つられてしまう。
﨑谷:それが良い風にでる時もあれば、4人とも傾いてしまう時もある。それが違うよね。
富岡:そういう時にも頑張って続けていこうと。それが難しいんですよ。うまくいっている時は、相乗効果で楽しいのですが、色々なコンディションがありますから。でも基本的にアンサンブルのやり方は変えたくない。
﨑谷:ウェールズQでやっていることが、他では通用しなかったりもします。スイッチを切り替えるので。「どうやっているの?」と聞かれたりもするのですが、すぐはできないと思いますね。
富岡:長く続けているというのもありますし、音楽的にも同じ先生に習ったというのも大きいですね。
横溝:僕はシュミット先生に直接会ったことはないのですが、この3人を通して分かることはあります。彼らがどういうアプローチで音楽を考えて、やろうとしているか、合わせをする前の段階で先に分かりますね。﨑谷だったらこうくるだろう、三原だったらこうしてくれって言ってくるだろうなと。そういうことがだいたいイメージできるようになりました。
﨑谷:それが一緒に弾くコツだよね。相手がどうくるかが、音を出した段階でもう分かるということ。
富岡:今いろいろな必要な段階を経て、音楽的なこと、アンサンブルすること、両方ともが同じ方向を向いている。みんなが音楽をぶつけあって和解していく、というのではなく、最終的に、こうなりたくて、そのための過程をふんで、訓練をしてきたという結果を見せています。
﨑谷:それから、説明できないことは意外にやっていません。(演奏が)奇抜に聞こえたりするようなのですが、奇をてらったり、何か新しいことをしてやろうという変な発想もない。自分は感覚的な人間なのですが、「こう感じる」「こういう風にしたい」と思った時、それはなぜかというバックグラウンドが、自分ひとりでは分からなくても、他のメンバーが作ってくれればそれでいいんです。でもそのバックグラウンドがないと、説得力がないですよね。それを4人で創っていく。例えば三原は、最初からきちんとスコアを読み込んでくるタイプだから、僕がやっていることが間違っている時など、きちんと言ってくれる。ではどうしようか、となる。
富岡:こうなるまでに、いろんな過程がありました。アンサンブルのやり方や、音程の合わせ方など。今やっていることがすべて正解とは思いませんが、今やっていることが最高だと思って、ずっとやっています。
本人たちが一番驚いたというミュンヘン国際音楽コンクール第3位入賞から、留学、ヨーロッパでの舞台など、様々な経験や葛藤を超えて、今4人で弾くのが充実していて楽しくてたまらない様子。これから3年間、磨き込んできたクァルテットの、さらなる音楽探究への旅にぜひご同行ください。